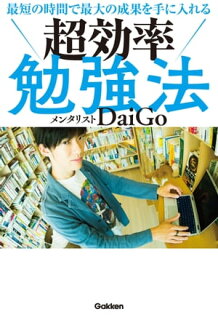日本経済新聞社が主催している日経TESTが、今、様々な企業で昇格試験などに取り入れられています。
しかしこの日経TEST、「公式テキストや日経新聞を読むだけではまず点が取れない」という、かなりクセのあるテストなんです!
でも、安心してくださいね。
忙しいあなたのために、最短2週間で600点以上のスコアを狙える勉強法をお教えします!
実際に私が2週間の勉強期間で620点を取った勉強法です!
ちょっと長いですが、スコアアップに役立つ情報を盛り込んでいますので、ぜひお読みください!
- 日経TESTの構成を知ろう
- 絶対に間違えないで!日経TEST対策の教材
- カンタンマスター!日経TEST勉強法
- 日経TEST勉強方法はどれぐらいやればいいの?
- 日経TESTの勉強にオススメのアプリ!
- 日経TESTの過去問はどうやって入手するの?
- (参考)私の日経TEST体験談
- まとめ 日経TEST勉強法は「広さ」より「深さ」!
日経TESTの構成を知ろう
まず最初に、日経TESTがどんな試験なのかを把握しましょう。
日経TESTの問題は5つのカテゴリで構成されており、1000点満点です。
・ 実践知識
・ 視野の広さ
・ 知識を知恵にする力
・ 知恵を活用する力
すべて4択問題のマークシート式で、記述する問題は一切ありません。
この4択がなかなか曲者で、2つまでは絞り込めても、どちらにするかかなり迷うような選択肢が多いんです。
また、出題範囲とされる公式テキスト(最新版)に載っていないような問題も沢山でてきます。
よって、いくら時間をかけて勉強をしても、方向性を間違うとまったく点がとれないのが日経TESTなんです。
日経TESTは過去問題集のようなものもなく、配点ロジックも明らかにされていません。
絶対に間違えないで!日経TEST対策の教材
日経TESTでは何の教材を使うかでほぼ命運がわかれます。
以下の記事に「オススメ教材」「NG教材」をまとめましたので、勉強を開始するまえに必ず見ていただくことをおすすめします。
参考【2022最新版】日経TESTの勉強におすすめの教材について - モエルライフ。
カンタンマスター!日経TEST勉強法
では、いよいよ「公式テキスト&問題集」を使った具体的な勉強方法にはいっていきます。
この勉強方法は、DaiGoさんの「超効率勉強法」がベースになったもので、実際に私も効果を実証しています。
日経TESTに限らずあらゆる試験や資格の勉強法にも役立ちますので、是非マスターしましょう。
本自体も大変面白いので、興味がある方は是非読んでみてくださいね。
①まずは問題を解くべし!
あなたに経済に関する知識がほとんどない場合、ついテキストを最初から読みたくなると思います。
その気持をぐっとこらえて、各章の終わりに設けられた練習問題を最初に解いていってください。
そんなの解けるわけない? もちろんそれでも構いません。
いきなり問題を解く理由は、「わからない単語」あぶり出すことにあるので大丈夫です。
問題を解いた後は、正解・不正解に関わらず解説をしっかり読みましょう。
「うーん、解説も何を言っているのかわからない・・・」となるかもしれませんが、大丈夫。
解説を読んで「わからなかった単語」もすべてマークしておきましょう。
このマークした単語が、あなたが日経TESTを受けるまでにマスターしておくべき重要なポイントとなります。
②問題を解いたあとに、テキスト部を読みはじめよう
設問と解説でわからない単語をマークし終えたら、初めてテキスト部分を読み始めましょう。
ここでも問題を解いたときと同様に、わからない単語や考え方が出てきたらマークしておき、あとでGoogleなどで調べます。
ここで絶対にやってはいけないのは、設問に対する答えのパターンを暗記することです。
これをやると再び同じ問題を解いたときに正答率があがるため、つい勉強が進んで気になりますが、「流暢性の罠」と呼ばれる現象なので注意しましょう。
「流暢性の罠」とは心理学用語で、同じ問題を繰り返し解いたりマーカーを引くことで「学習が進んでいる」と錯覚することをさします。単調なパターンを記憶しているだけなので、応用力はほとんど身につきません。
日経TESTの勉強法の最大のポイントは「できるだけ多くの経済ワードに触れ、理解を深めていくこと」です。
いくらテキストの例題になれても、本番では意味をなさないことを覚えておきましょう!
③わからなかった単語を元に、自分で問題を作って解こう
「マークした単語」が集まってきたら、ここからが本番です。
今度はその単語をもとに、あなた自身が問題を作ってください。
たとえばこんな感じです。
A.札幌大通公園
日経TESTでは4択ですが、あなたのオリジナル問題は一問一答式で構いません。
他には「○○について説明せよ」「○○なのはなぜか?」というように、概念を把握していないと解けない問題もいいですね。
とにかく「わからなかった単語を即問題化し、自ら解いていく」というのがこの勉強法の核心部分です。
問題をストックしていくのはノートや単語カードで構いませんが、後述する「アプリ(無料)」を使うと便利なので是非使いましょう。
日経TESTの勉強の流れ
日経TESTの勉強法は以上ですが、流れを整理するとこのようになります。
- STEP1いきなり問題を解く「日経TEST公式テキスト&問題集」のテキスト部を読み始めるのではなく、いきなり問題を解きましょう。
- STEP2解説やテキストを読むわからない単語などあればしっかりストックし、意味を調べておきます。
- STEP3自分で問題を作る「STEP2」で収集した単語をもとに自分で問題を考えます。一問一答だけではなく、「この理由を以下から選べ」という風に「考え方」を問うような問題もつくりましょう。
- STEP4問題を解く問題が出来たら、解いてみます。一度解いて終わりではなく、間隔をおいて何度も解きましょう。
- STEP5STEP1にループこの循環を続けていくと、高度な「疑問」が生まれ、問題も深化していきます。
私は最初に「日経TESTは公式テキスト&問題集の1冊で十分」とお伝えしました。
「情報量が足りないんじゃないの?」と思われたかもしれませんが、実際にこのやり方で勉強をしていくと、テキストの中に沢山の問題のネタが見つかるようになります。
さらにその単語を調べていくと、派生して疑問が生まれたり、別の角度から問題を思いついたり・・・という風に、まるでシナプスが繋がるように広がっていきます。
1冊のテキストでも十分な情報量が得られますので、まずは公式テキスト&問題集をしっかり掘り下げていくことをオススメします。
日経TEST勉強方法はどれぐらいやればいいの?
試験本番まで2週間や1ヶ月など期間が短い場合、基本的に1日あたりの勉強時間は多いほどよいです。
ただし人間の集中力が続く期間は短いので、「5時間ぶっ通し」みたいな勉強のやりかたは逆に効率が悪くオススメできません。
私の場合、試験までの期日は約2週間でしたが、1日の勉強時間はトータルで4時間ぐらいでした(うち、通勤中のアプリでの学習が1時間ほど)。
ただしこのやり方にはコツがあって、30分おきに5分から10分の休みをとるようにしました。
これはポモドーロテクニックと呼ばれる時間術がベースになっており、集中力が低下することがなく、効率的に勉強できるのでオススメです。
あなたの学習の参考になれば幸いです。
日経TESTの勉強にオススメのアプリ!
ここでは日経TESTの勉強にオススメのアプリをご紹介します。
といってもここでご紹介するのは「経済テストを出題するアプリ」ではありません。
経済テストを出題するタイプのアプリは、情報が古いのでまったくオススメできません。
DaiGoさんの「超効率勉強法」にも詳しく書かれていますが、学習のポイントは忘れかかったタイミングで復習することです。
この「忘れかかったタイミング」というのが非常に重要で、単に翌日に問題を復習すればOKというわけではありません。
「エビングハウスの忘却曲線」なんてものもありますが、復習のタイミングまで管理するのはなかなか大変です。
そこでおすすめしたいのが、DaiGoさん監修の分散学習帳というアプリです。
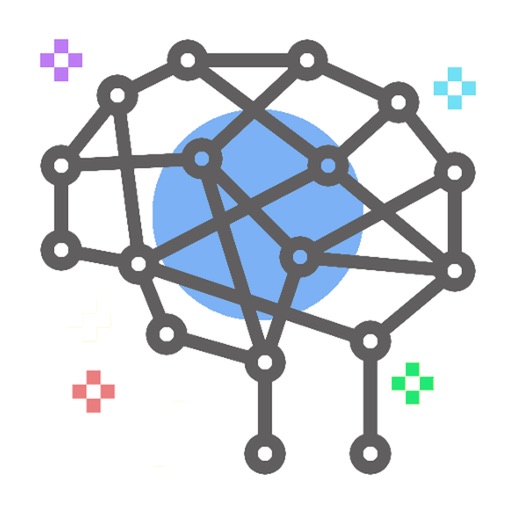
このアプリは大変よく出来ていて、自分で作った問題を記録できるだけでなく、適切な期間をおいて再出題してくれるので大変便利です。
しかも無料!
私は日経TESTのテキストを読みこみながら、ひたすらこのアプリに問題を作って打ち込んでいました。
鉛筆で書くような勉強はほとんどしなかったです。
日経TESTの過去問はどうやって入手するの?
一般的なテスト対策では過去問を解きまくるのは鉄板です。しかし、大変残念なことに、日経TESTの過去問は公表されてません。
日経TESTの勉強のしにくさの要因はここです
ただし、日経新聞社の「採用テストの過去問」であれば公式サイトからDLできます。
LINKhttps://www.nikkei.co.jp/saiyo/recruit/previous.html
ヤマをはるという点ではまったく役に立ちませんが、「どんなレベル感の出題がされるか」は把握できますので、過去2年分ぐらいまで解いてみることをオススメします。
ただし、この問題はすでに情報が古いため、深堀りしてもあまり意味はありません。
あくまで出題の傾向や難易度を把握しておく程度にとどめておきましょう。
(参考)私の日経TEST体験談
ここからは私の日経TEST体験談です!
私のやり方を取り入れるかどうかはお任せしますが、これから日経TESTを受けるという方の参考になれば幸いです。
配点の高い問題から着手!
日経TESTを受ける前に、私は「ある作戦」を立てていました。
それは問題冊子の後ろから解いていくということです。
日経TESTの試験時間は80分。
一見長いようですが、問題数が100問あるため、実際は1問に1分もかけられません。
日経TESTは後半になるほど長文やグラフ読解など配点が高そうな問題が出てきます。
ここをしっかり取っていくんや…!
配点の低い「一問一答」の4択ごときに時間をかけるわけにはいきません(さらに一問一答も悩む選択肢のものが多い)。
とはいえ、解答がブランクの問題が出ることはさけたいので、時間配分に気をつけながら、問題をさかのぼって解いていきました。
解答が不安な問題のみ、見直し用にマーキング!
試験で「見直し」は鉄則ですが、日経TESTは「おそらく全問を見直す余裕は無いだろう」と思っていました。
そこで予め「あってるか不安だな」という問題のみ、見直し用にマーキングをしたのです。
一通りとき終わった時点で、やはり残り時間は少なめ。
「配点の高そうな問題」を見直すのはもちろん、「マーキング済の問題」を優先的に見直すことで、時間を有効活用&正答率UPを目指しました。
マークシートのズレがないかもチェック!
日経TESTは解答の見直しだけでは十分ではありません。
というのも、日経TESTはマークシート(※PC受験もあるようです)のため、万一解答がずれていた場合、元も子もなくなるからです。
そのため、最後の10分は、「マークシートのズレがないか」を点検するために費やしました。
ちょっと勿体ない気もしますが、最低限の保険でもありますので、一通りマークを見直す時間は確保しておくことをおすすめします。
体験談は以上です。あなたの参考になれば嬉しいです!
まとめ 日経TEST勉強法は「広さ」より「深さ」!
今回ご紹介した勉強方法は、限られた時間をいかに有効活用するかがポイント。
決して頭のよくない私でも短期間で600点以上とれたので、あなたでも再現性がある方法だと思っています。
とはいえ、最初のテキスト選びで失敗すると結構大変なので、以下の記事もぜひ読んでおいてください。
参考【2022最新版】日経TESTの勉強におすすめの教材について - モエルライフ。
また、上の記事でもご紹介していますが、試験まで1ヶ月以上あるという方は楽天マガジンで「日経TRENDY」を読んでおくと時事問題・トレンド問題への備えになります。
- 日経TRENDY他、450誌以上が月418円(税込)で読み放題
- 使っていない楽天ポイントで支払いOK
- 使いやすいアプリ!もちろんPCでも読める!

リンク先:https://magazine.rakuten.co.jp/
登録まで約5分、解約はわずか6クリックで簡単です!
日経TEST本番はとにかく時間が足りないので、配点の多いところを確実にとっていくことがポイントです。
この記事によってあなたがスコアアップすることを心から願っています!